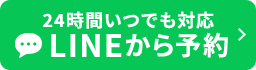のどがつかえる、むせるような咳にお悩みですか?
 のどがつかえる感じや、むせるような咳が頻繁に出る場合、さまざまな原因が考えられます。こうした症状は、一時的な風邪やアレルギーによるもののこともありますが、嚥下障害が原因となっていることもあります。嚥下障害では、食べ物や飲み物が上手く飲み込めず、気道に入ってしまうことで、咳やむせが起こります。嚥下障害によるこうした症状が続くと、誤嚥性肺炎などの合併症を引き起こすリスクが高まりますので、注意が必要です。
のどがつかえる感じや、むせるような咳が頻繁に出る場合、さまざまな原因が考えられます。こうした症状は、一時的な風邪やアレルギーによるもののこともありますが、嚥下障害が原因となっていることもあります。嚥下障害では、食べ物や飲み物が上手く飲み込めず、気道に入ってしまうことで、咳やむせが起こります。嚥下障害によるこうした症状が続くと、誤嚥性肺炎などの合併症を引き起こすリスクが高まりますので、注意が必要です。
また、嚥下障害だけでなく、逆流性食道炎やのどの炎症、甲状腺疾患、神経疾患が原因となることもあります。適切な治療のために、まずは原因を特定することが重要です。
こうした症状はありませんか?
「のどがつかえる」や「むせるような咳がよく出る」に関しては、以下のような表現をされることもあります。当てはまる症状がありましたら、嚥下障害の治療も積極的に行っている当院までご相談ください。
- のどに異物感がある
- のどが引っかかる感じがする
- 食べ物や飲み物がスムーズに飲み込めない
- 咳が出るときにむせることがある
- 物がのどに詰まったように感じる
- 吸い込む際にむせることが頻繁にある
- 咳き込むとのどが刺激される感じがする
など
のどがつかえる原因
嚥下障害
嚥下障害は、食べ物や液体をスムーズに飲み込むことができない状態であり、脳卒中や認知症、パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、多発性硬化症、筋ジストロフィー、脳性麻痺などの神経疾患が原因となることが多いです。神経信号の伝達が妨げられ、嚥下に必要な筋肉の動きが制限されます。嚥下障害により、誤嚥が起こると、肺炎などの重篤な合併症を引き起こすリスクがあります。食事中のつかえ感やむせることが増えるため、早期に医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けることが重要です。
食道炎
食道炎は、食道の内壁が炎症を起こす状態で、主に逆流性食道炎が一般的です。胃酸が食道に逆流することで、食道の粘膜が傷つき、痛みや不快感を引き起こします。また、食道炎はヘルペスウイルスなどのウイルスや、カビの一種であるカンジダなどによる感染症、内服薬が食道に長時間留まること(薬剤性食道炎)でも発生します。食物が通過しにくくなり、のどに異物感を感じることがあります。診断には内視鏡検査が必要なことがあります。治療は原因により異なりますが、逆流性食道炎の場合には生活習慣の改善や胃酸分泌を抑える薬剤が用いられます。
食道狭窄
食道狭窄は、食道の内部が狭くなり、飲食物が通過しにくくなる状態です。原因には、良性のものでは慢性の逆流性食道炎や食道アカラシア、悪性のものでは食道がんなどの腫瘍、食道がん治療後の瘢痕が含まれます。狭窄が進行すると、食事中に食べ物が引っかかる感じや痛みが生じ、しばしばむせることもあります。診断は内視鏡検査や画像診断で行われ、治療には胃酸の分泌を抑える薬剤に加え、食道拡張術や手術が考慮されることがあります。適切な処置を行わないと、栄養不足や脱水症状を引き起こす可能性があります。
食道がん
食道がんは、食道の細胞が異常に増殖し、悪性腫瘍を形成する病気です。初期には症状があまり現れないことが多いですが、進行すると、飲み込みづらさやのどのつかえ感が生じます。また、体重減少や嚥下時の痛み、胸の圧迫感も見られることがあります。診断には内視鏡検査が必要で、早期発見が重要です。治療法としては、手術、放射線療法、化学療法が選択され、進行具合や患者の状態に応じた治療が行われます。
舌がん
舌がんは、舌の表面に発生する悪性腫瘍で、特に喉の奥に近い部分にできると、飲み込み時の痛みやつかえ感を引き起こすことがあります。初期症状としては、舌のしこりや白斑(白い斑点)、出血などが見られます。診断には口腔内の検査や生検が必要で、治療には手術、放射線療法、化学療法が含まれます。早期の発見と治療が重要です。
咽頭がん
咽頭がんは、のどの奥にある咽頭に発生するがんで、飲み込む際に痛みやつかえ感が生じることがあります。また、声のかすれや咳が出ることもあります。主なリスク要因には喫煙、飲酒があり、特に中高年に多く見られます。上咽頭癌はEBウィルス、中咽頭癌はヒトパピローマウィルス(HPV)の感染が発症リスクを高めるといわれています。診断は内視鏡検査で行われ、治療には手術、放射線療法、化学療法が検討されます。
甲状腺腫瘍
甲状腺腫瘍は、甲状腺にできる腫瘍で、良性・悪性にかかわらず、周囲の組織に圧迫をかけることで喉のつかえ感を引き起こすことがあります。特に、甲状腺の肥大や腫瘍が大きくなると、食事中に異物感を感じたり、呼吸に影響を及ぼすこともあります。診断には超音波検査、甲状腺に針を刺して細胞を診る検査(細胞診)が行われます。治療は手術ですが、無治療経過観察が可能なこともあります。腫瘍の性質や大きさによって治療方針が変わるため、専門医の診察が必要です。
喉頭アレルギー、アトピー性咳嗽
いずれもアレルギーが原因となる疾患です。喉頭アレルギーは喉の粘膜、アトピー性咳嗽は気管、気管支の中枢が炎症を起こします。特に花粉やハウスダストなどによるアレルギーが一般的な原因です。のどのかゆみや腫れ、つかえ感が生じ、時にはむせるような咳を伴うことがあります。診断は血液検査やアレルギー検査によって行われ、治療には抗ヒスタミン薬内服やステロイドの吸入が有効です。また、アレルゲンを避けることが重要です。
薬剤性の副作用
一部の薬剤、特に抗コリン作用のある薬(抗ヒスタミン作用を持つ鼻水や痒みを抑える薬剤、排尿障害の薬剤、抗うつ薬など)や一部の降圧薬(カルシウム拮抗薬や利尿薬)は唾液分泌を減少させ、口腔内を乾燥させることがあります。これにより、食物がのどを通りづらく感じたり、むせやすくなることがあります。薬剤の変更や用量調整が必要な場合があります。症状が現れた場合は、処方してもらった医師に相談してみましょう。
精神的要因による咽頭の不快感
ストレスや不安、緊張が原因で、咽頭過敏症(咽喉頭異常感症)と呼ばれる状態が引き起こされることがあります。特に、社会的な状況や特定の場面で緊張が高まると、喉の筋肉が収縮し、つかえる感覚が生じることがあります。のどの異物感を伴い、食事を取るのが難しくなることもあります。精神的な要因があれば、ストレスの緩和や、その原因の治療が必要です。また、漢方薬が有効なことがあります。
むせるような咳が
よく出る原因
嚥下障害
 嚥下障害は、食べ物や液体を正常に飲み込むことができない状態で、これにより誤嚥が生じると、むせるような咳が出ることがあります。高齢者や神経疾患(脳卒中、認知症、パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、多発性硬化症、筋ジストロフィー、脳性麻痺など)を持つ方に多く見られ、飲み込む際にのどの筋肉の協調がうまくいかないことが原因です。誤嚥が続くと、肺炎を引き起こすリスクも高まります。診断には嚥下機能検査や内視鏡検査が用いられ、治療には嚥下訓練や食事の見直しが行われます。
嚥下障害は、食べ物や液体を正常に飲み込むことができない状態で、これにより誤嚥が生じると、むせるような咳が出ることがあります。高齢者や神経疾患(脳卒中、認知症、パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、多発性硬化症、筋ジストロフィー、脳性麻痺など)を持つ方に多く見られ、飲み込む際にのどの筋肉の協調がうまくいかないことが原因です。誤嚥が続くと、肺炎を引き起こすリスクも高まります。診断には嚥下機能検査や内視鏡検査が用いられ、治療には嚥下訓練や食事の見直しが行われます。
長引く咳
近年、咳が長引く患者さんが増えてきています。発症後3~8週間続く場合を遷延性咳嗽、8週間以上の場合を慢性咳嗽に分類されます。咳喘息が頻度として多く、アトピー性咳嗽・喉頭アレルギー、副鼻腔気管支症候群、逆流性食道炎、感染後咳嗽などが鑑別になります。 治療は原因による異なりますが。胸部レントゲンを撮影し、肺の異常の確認も重要です。
喘息・咳喘息
喘息は、気道が慢性的に炎症を起こし、むせるような咳や喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒュー音)が特徴的な病気です。一方、喘鳴を伴わない、咳喘息というものもあります。咳喘息は放置すると、喘息に移行することがあり注意が必要です。原因として、ハウスダスト、花粉などのアレルギー物質、タバコの煙などが知られています。夜間や早朝に咳が悪化することが多く、アレルゲンや運動、寒暖差や、寒冷刺激が引き金になることがあります。咳は乾いたものであることが多く、呼吸困難を伴う場合もあります。診断には血液検査、アレルギー検査、胸部レントゲン検査、呼吸機能検査などを行います。治療は吸入ステロイドや気管支拡張薬が中心です。
喉頭アレルギー、アトピー性咳嗽
いずれもアレルギーが原因となる疾患です。喉頭アレルギーは喉の粘膜、アトピー性咳嗽は気管、気管支の中枢が炎症を起こします。特に花粉やハウスダストなどによるアレルギーが一般的な原因です。のどのかゆみや腫れ、つかえ感が生じ、時にはむせるような咳を伴うことがあります。診断は血液検査や胸部レントゲン検査、アレルギー検査などによって行われ、治療には抗ヒスタミン薬内服やステロイドの吸入が有効です。また、アレルゲンを避けることが重要です。
感染後咳嗽
かぜのあとに、熱や喉の症状が改善しているにもかかわらず、咳のみ持続する疾患です。徐々にでも自然軽快傾向であることも特徴です。原因はよく分かっていませんが、かぜを契機に咳感受性が亢進したり、咳を起こす物質を分解する酵素の活性低下することが原因として考えられています。必要に応じて、血液検査、胸部レントゲン検査、呼吸機能検査などを行い、他の疾患を除外します。治療は通常の咳止め、漢方、抗ヒスタミン薬、吸入薬を使用します。
副鼻腔気管支症候群
上気道(喉より上)と下気道(気管〜肺)の炎症を合併した病態です。他の長引く咳の原因と異なり、痰が出ることが特徴です。上気道の炎症は慢性副鼻腔炎であり、鼻汁、鼻づまりといった症状が伴います。下気道の炎症は慢性気管支炎や気管支拡張症などがあります。他の長引く咳と鑑別するため、レントゲンなど胸部画像検査も重要になります。治療には少量のマクロライド系抗生剤の長期内服が有効です。この治療は抗菌作用にために行うのではなく、マクロライド系抗生剤の免疫を調節し炎症を抑える作用や、線毛運動(気道の異物を排除する動き)の亢進の作用を期待して行われます。
副鼻腔炎
副鼻腔炎は、副鼻腔の炎症によって生じる病気で、鼻水が喉に流れ込む「後鼻漏」が原因でむせるような咳を引き起こすことがあります。のどが刺激されて咳が出ることがあります。副鼻腔炎は、細菌・ウイルス・カビの感染やアレルギーなどが原因となることが多いです。診断にはレントゲンやCT検査や内視鏡検査が用いられます。治療は感染であれば抗生物質などの病原体に対する治療、抗ヒスタミン薬やステロイド点鼻薬(鼻のスプレー)などが使用されます。
胸やけ(逆流性食道炎)
逆流性食道炎は、胃酸が食道に逆流し、胸やけやむせるような咳を引き起こす病気です。食道の下部が緩んだり、胃の内容物が上がってくることで、のどに刺激を与え、咳が誘発されます。特に横になったり、食後に症状が悪化しやすく、のどの違和感を伴うことがあります。診断には内視鏡検査が行われ、治療は生活習慣の改善や薬物療法(プロトンポンプ阻害薬やヒスタミンH1受容体拮抗薬などの胃酸を抑える薬剤)が中心となります。生活習慣の改善としては、カフェインやアルコール、脂っこいものなどを控えることが有用です。また、食後は横になったり前かがみになるなど、胃酸が逆流しやすい体勢にならないことも大事です。
感染症
細菌やウイルスによる感染症もむせるような咳を引き起こす原因となります。肺炎、風邪、インフルエンザ、新型コロナウィルス感染症、百日咳やマイコプラズマなどが原因となります。咳は湿性(痰がからむ)のことが多いですが、マイコプラズマや百日咳は乾性(痰がからまない)のことが多いです。診断は原因によりますが、血液検査や胸部レントゲン、鼻咽頭ぬぐい液などでの迅速抗原検査が行われます。治療は対症療法や抗生物質が使用されます。咳が長引く場合や重篤な症状がある場合は、早めに受診することが重要です。
肺炎
肺炎は、肺の炎症を伴う感染症で、主に細菌が原因となり、稀にウイルス、真菌も原因となることがあります。むせるような咳が出ることがあり、特に感染が進行すると痰が絡む咳や高熱、息切れが見られることがあります。診断には血液検査や胸部レントゲン検査が行われ、治療は抗生物質など原因となる病原体に有効な薬剤を投与します。重症の場合は入院が必要になることもあります。
胸膜炎
胸膜炎は、肺を覆う膜が炎症を起こす状態で、むせるような咳が出ることがあります。胸痛や呼吸困難を伴うことが多く、特に深呼吸や咳をすると痛みが増すことがあります。肺炎や結核など感染症に伴うものがほとんどです。その他に、関節リウマチや全身性エリテマトーデスなどの自己免疫疾患や、癌が原因となることがあります。診断には血液検査、胸部レントゲン検査やCT検査が用いられます。治療はそれぞれの原因に応じて行われますが、胸膜炎に伴い肺に水が貯まることがあり(胸水)、場合によっては胸腔ドレナージといって肺の水を抜く処置が必要になることもあります。
甲状腺疾患
甲状腺が腫大したり、甲状腺の腫瘍があることによって、気管を圧迫し、むせるような咳を引き起こすことがあります。咳以外にも、のどの違和感や圧迫感を伴うことがあります。また、バセドウ病や橋本病では、甲状腺ホルモンの異常が見られることもありま。診断には血液検査や超音波検査が行われます。
心不全
心不全が進行すると、肺に水がたまり、むせるような咳が生じることがあります。特に夜間に横になると咳が悪化する「夜間発作性呼吸困難」が見られることがあります。心不全の他の症状には、息切れ、疲労感、むくみなどがあります。診断には心臓超音波検査や胸部レントゲン検査が行われ、治療は利尿剤や心不全の原因に応じた治療が必要です。
慢性閉塞性肺疾患(COPD)
COPDは、主に喫煙や長期間の有害物質への曝露によって引き起こされる慢性の気道疾患です。肺の気道が狭くなり、空気の流れが悪くなります。むせるような咳や痰が多く出ることがあり、特に朝起きたときに悪化します。進行することで、呼吸困難や運動時の疲れやすさなどが見られるようになります。診断には胸部レントゲン検査や肺機能検査が必要です。治療は気管支拡張薬の吸入が主に行われます。
のどがつかえる、むせるような咳が出ることに関する
よくある質問
むせるような咳が続くとどうなりますか?
むせるような咳が続くと、喉や気道に刺激を与え、さらなる咳や喉の痛みを引き起こすことがあります。また、誤嚥による肺炎のリスクもあるため、早めに受診することが重要です。
むせるような咳が出るとき、どうすればいいですか?
むせるような咳が出た場合、まずは落ち着いて、深呼吸をしてリラックスすることが大切です。無理に咳をし続けると、かえって喉を傷めることがあります。水を少しずつ飲むと良いでしょう。
のどのつかえ感があるとき、食事に注意することはありますか?
のどがつかえる感覚がある場合は、食事の内容や食べ方に注意が必要です。柔らかい食べ物を選び、しっかりと噛んでから飲み込むことが推奨されます。また、液体は少しずつ飲むようにしましょう。
のどがつかえる感覚があるとき、どのような食べ物を避けるべきですか
のどがつかえる感覚がある場合は、硬い食べ物や粘り気のある食材、乾燥したものを避けることが望ましいです。例えば、ナッツ、ポテトチップス、餅などは詰まりやすく、逆に柔らかくて水分を多く含む食材(スープやヨーグルトなど)を選ぶと良いでしょう。
むせるような咳を改善するために、自宅でできる対策はありますか
むせるような咳を改善するためには、温かい飲み物を摂取してのどを潤すことや、加湿器を使用して湿度を保つことが効果的です。また、のどを刺激する煙草や香辛料を避けることも大切です。
のどがつかえる症状がある場合、どのくらいの期間様子を見るべきですか?
のどがつかえる症状が数日以上続く場合や、痛みや発熱や体重減少など他の症状を伴う場合は、早めに受診するようにしましょう。
高齢者に多く見られるのどがつかえる症状にはどのような原因がありますか?
高齢者では、嚥下機能の低下や神経系の疾患(パーキンソン病、脳卒中、認知症など)が原因となることが多いです。また、口腔内の乾燥や入れ歯の不具合も影響することがあります。
食事中にむせたときの対処法は何ですか?
食事中にむせた場合は、まずは落ち着いて深呼吸し、水分を少しずつ摂ることが効果的です。無理に咳をし続けると、のどを傷める原因となるため、状況に応じてゆっくりと対応してください。