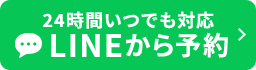嚥下外来とは
 日本では超高齢社会に伴い、嚥下障害を抱える方が増えています。加齢により筋力や神経などの働きが低下し、喉頭(のどぼとけ)の位置も下がるため、嚥下機能も衰えてしまいます。(75歳以上の約3割が誤嚥を経験するという報告もあります。)
日本では超高齢社会に伴い、嚥下障害を抱える方が増えています。加齢により筋力や神経などの働きが低下し、喉頭(のどぼとけ)の位置も下がるため、嚥下機能も衰えてしまいます。(75歳以上の約3割が誤嚥を経験するという報告もあります。)
嚥下機能の低下によって、食べ物や唾液が誤って肺に入り、誤嚥性肺炎が発症することがあります。特に“水”のようなさらさらした液体は、口から食道までの通り道を素早く通過するため、誤嚥のリスクが高まります。また、胃の中の食べ物が逆流することによる誤嚥や、餅などののどに張り付きやすい食べ物による窒息事故も問題となっています。認知機能が低下している患者さんにおいては、食べ物を口の中に溜め込んだり丸呑みする傾向があり、誤嚥や窒息のリスクがさらに高まります。
当院では、摂食・嚥下障害看護認定看護師による嚥下外来を行っています。摂食(食べるまでの動作)や嚥下機能の評価、栄養状態や脱水の評価、口腔ケアの方法、安全な食事の仕方や食べ物の選択などを総合的に判断し、誤嚥性肺炎や脱水、低栄養にならないようにお手伝いさせていただきます。
嚥下外来の受診を
おすすめする方
- 肺炎の診断をされたことがある方
- 痩せてきた(体重減少が見られた)方
- 物が飲み込みにくいと感じる方
- 食事中にむせる方
- 水分を飲むときにむせる方
- 食事中あるいは食後にのどがゴロゴロする方(痰がからむなど)
- 食事中や食後に声が変わる方
- のどに食べ物が残る感じがする方
- 食事に時間がかかるようになった方
- 硬いものがたべにくくなった方
- 口から食べ物がこぼれるようになった方
- 口の中に食べ物が残る方
- 食べ物や酸っぱい液が胃からのどに戻ってくる方
- 胸に食べ物が詰まった感じ(食べ物が残った感じ)のする方
- 夜、咳で眠れないことや目覚めることがある方
- 声のかすれが気になる方
- 食後に呼吸が苦しくなる方
など
嚥下外来のご予約
完全予約制となります。(お一人1時間の枠となっています。)
下記より、ご予約ください。
曜日によって受付終了の時間が異なります。
嚥下外来の流れ
STEP01
問診・体重測定
摂食・嚥下障害看護認定看護師による問診・体重測定の実施を行います
(事前に問診票にご記入いただきます。)
STEP02
診察・評価
医師による診察・評価を行います。
必要時、採血や胸部レントゲン検査、呼吸機能検査などの検査を実施します。
STEP03
嚥下リハビリ・指導
摂食・嚥下障害看護認定看護師による嚥下リハビリや指導(口腔ケアや食事の仕方、姿勢調整など)を行います。
STEP04
スケジュールのご相談
飲み込みの状況(嚥下機能)により、今後の来院スケジュールを相談いたします。
*嚥下内視鏡検査などの精密検査が必要な場合は、連携する医療機関にご紹介いたします。結果を基に安全な食事の支援をさせていただきます。
嚥下外来の費用に関して
検査や処方、他の病気の診察がない場合は下記が目安となります。
初回(初診時)の費用
| 3割負担 |
約1,500円 |
|---|---|
| 2割負担 |
約1,000円 |
| 1割負担 |
約500円 |
2回目以降 (再診時)
| 3割負担 |
約990円 |
|---|---|
| 2割負担 |
約660円 |
| 1割負担 |
約330円 |
嚥下障害の原因
加齢
年を重ねると筋力や神経の機能が低下します。特に嚥下に関係する舌、のどの筋肉が弱くなり、食べ物をスムーズに飲み込むことが難しくなります。また、喉頭(のど仏)の位置が下がるため、食べ物が気道に入りやすくなり、誤嚥のリスクが増します。さらに、のどや咽頭の反射や反応が鈍くなるため、食べ物が気管に入ったときにむせにくくなることもあります。
神経系疾患
脳卒中や認知症、パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、多発性硬化症、筋ジストロフィ、脳性麻痺など、神経系に関わる病気は嚥下機能に重大な影響を与えます。これらの疾患では、脳や神経が食べ物を飲み込む筋肉を正常に働かせることができなくなるため、嚥下の動作が遅くなったり、適切にできなくなります。特に脳卒中後は嚥下障害が起こることが一般的で、患者さんの多くが誤嚥性肺炎を引き起こすリスクが高まります
認知症
認知症が進行すると、食べ物を正しく認識し、嚥下の動作を正常に行う能力が低下します。食事を食べ物として認識できず、口の中に溜め込んでしまうことや飲み込むことができない、一気に飲み込んでしまうなど窒息や誤嚥のリスクが高まります。また、食事に集中できず、食事を途中でやめてしまうことや食器の使い方が分からなくなるなど、認知に問題が起きてしまうことで、食べる量が減り低栄養や脱水となってしまうこともあります。
咽頭・食道の構造的異常
咽頭や食道に腫瘍、ポリープ、狭窄(狭くなる状態)などがあると、物理的に食べ物が通りにくくなり、嚥下障害が発生します。特に咽頭や食道のがん、甲状腺の腫れなどがある場合、嚥下の際に痛みや不快感を伴うことが多いです。飲み込みを困難にし、固形物だけでなく液体を飲み込むことさえ難しくすることがあります。
手術後の影響
特に頭頸部や食道の手術後に嚥下障害が発生することがあります。腫瘍摘出や甲状腺手術、食道手術、または声帯や喉頭の部分的な除去が含まれます。手術によって神経が損傷したり、筋肉が弱くなったりすることで、正常な嚥下機能が損なわれることがあります。
薬の副作用
特定の薬剤、特に睡眠薬や鎮静剤が原因となり、嚥下障害が起こることがあります。薬の効果により、意識がぼーっとした状態で食事を取ると、飲み込みの反射やむせの反射が起きにくくなり、誤嚥性肺炎になるリスクが上がります。抗コリン薬(抗ヒスタミン作用を持つ鼻水や痒みを抑える薬剤、排尿障害の薬剤など)などは唾液の分泌を減少させ、口の中を乾燥させます。これにより、食べ物がスムーズにのどを通過しにくくなります。また、筋弛緩剤なども筋肉の働きを抑制するため、嚥下に関係する筋肉がうまく機能せず、飲み込みにくくなることがあります。
口腔(口の中)の状態や歯の問題
口腔(口の中)が清潔でない、乾燥しているなどの症状があると口腔の働きが上手く発揮できずに、食べ物の食べにくさや汚染された口の細菌が肺に入ることで誤嚥性肺炎を起こすことがあります。また、歯が抜けていたり、噛み合わせが悪いと、十分に食べ物を噛むことができなくなり、固形物を飲み込む際に嚥下が難しくなります。入れ歯が合っていない場合や口の中の感染症があると、痛みや違和感により食べ物を上手く噛むことができず嚥下を妨げることもあります。
逆流性食道炎
胃酸が食道に逆流し、食道やのどに炎症を引き起こす逆流性食道炎は、嚥下困難を引き起こすことがあります。食道が炎症を起こすと、飲み込む際に痛みが生じたり、食べ物がのどに引っかかるような感じを覚えることがあります。慢性的な逆流が嚥下障害を悪化させる場合もあり、逆流性食道炎の治療が必要です。
嚥下障害の検査
嚥下障害のスクリーニング
(問診・反復唾液嚥下テスト・改定水飲みテスト・フードテストなど)
摂食嚥下障害が疑われる患者さんを早期に発見し、その後の精密検査の必要性や対応に繋げていくために行います。問診では、飲み込みに関する事だけでなく食事習慣や食事環境、好きな食べ物・嫌いな食べ物など、食生活全般にも目を向け確認させていただきます。また、普段食べている食べ物をご持参いただき、実際に食べている様子を拝見する場合もあります。
栄養スクリーニング
嚥下障害により、口から食べられる量が少なくなる事で栄養障害や脱水が起きてしまうことがあります。体重測定や食事量・水分量の確認、血液検査(必要時)などで総合的な栄養状態を確認させていただき、栄養改善や脱水予防に向けたサポートをします。
呼吸スクリーニング
嚥下と呼吸は、密に関連しています。食べ物や飲み物を嚥下する際、呼吸は一時的に止まり、嚥下動作が終わったあとに呼吸が再開します。特に呼吸器疾患がある患者さんは、食事により呼吸が苦しくなり、誤嚥のリスクや低栄養になってしまうことがあります。酸素飽和度や呼吸の状態、胸部レントゲン・採血(必要時)などで総合的な呼吸状態を確認し、サポートさせていただきます。
口腔状態の確認
口腔の衛生状態や歯・舌の動きなどの口腔の状態は、食事を安全に食べる上でとても大切です。口腔の状態や口腔ケア習慣・方法を確認させていただき、適切な方法をアドバイスさせていただきます。
嚥下障害の精密検査には、嚥下内視鏡検査や嚥下造影検査があります。
嚥下内視鏡検査(VE)では、細い内視鏡を鼻から挿入し、のどの状態を観察します。食べ物や液体を飲み込む様子を直接見ることで、誤嚥の有無や嚥下の状態を確認します。
嚥下造影検査(VF)は、バリウムを含んだ食べ物や飲み物を飲み込みながらX線で撮影し、嚥下の状態を確認する方法です。これにより、食べ物がどのように移動し、誤嚥の有無や嚥下の状態を確認します。これらの検査が必要な際は、連携する医療機関をご紹介し、結果を基に安全な食事の支援をさせていただきます。
嚥下障害の対応
 嚥下障害の対応は、患者様の状態に応じてリハビリテーションと手術に分けられます。以下では、各対応法について詳しく説明します。
嚥下障害の対応は、患者様の状態に応じてリハビリテーションと手術に分けられます。以下では、各対応法について詳しく説明します。
リハビリテーション
リハビリテーションは、嚥下機能を回復させるための重要な手段です。リハビリは、間接訓練と直接訓練の2つの段階に分かれています。
間接訓練
間接訓練では、食べ物を使わずに口やのどの機能や呼吸を改善するためのトレーニングを行います。
口腔ケア
口腔ケアを行うことで、口の中の衛生状態を保つことや誤嚥性肺炎の予防、食べる・話すなどの口腔の持つ機能を向上させるなどの効果があります。また、唾液の分泌が増えることで食事の味を十分に感じられることも期待できます。具体的には、歯ブラシや粘膜ブラシなどを使用し、歯牙や舌、歯肉など口の中の清掃を行います。その際、口腔内をマッサージしたり、口腔の体操を行い機能の向上を図ります。口腔の乾燥など、気になる症状に対しても対応させていただきます。
リラクゼーション
首や肩の筋肉が緊張していると、嚥下が困難になります。ストレッチや深呼吸を通じて、体全体をリラックスさせることが重要です。腕を広げる運動や首・肩を回すことで、筋肉の緊張を和らげます。
口唇・舌・頬の訓練
安全に食べるためには、口や舌の運動が必要です。頬を膨らませたり、舌を動かすことにより、筋力を強化し、食べ物の取り込みや噛む動作、送り込みの動作をスムーズにします。
のどのアイスマッサージ法
口腔や咽頭の感覚を改善するために、凍らせた綿棒を使って口腔内や咽頭を刺激します。これにより、飲み込みの反射を高めることが期待できます。
嚥下おでこ体操
 食べ物は咽頭へ送られてきた際、喉頭(のど仏)挙上という嚥下の反射が起こり、食べ物が食道へ送られます。嚥下おでこ体操では、特に喉頭挙上に関わる筋の筋力強化を行います。
食べ物は咽頭へ送られてきた際、喉頭(のど仏)挙上という嚥下の反射が起こり、食べ物が食道へ送られます。嚥下おでこ体操では、特に喉頭挙上に関わる筋の筋力強化を行います。
手の平の付け根あたりをおでこに当てて抵抗を加え、おへそをのぞき込むように、顎を引きます。おでこと手の平を押し合います。
呼吸訓練
咳をしっかり行うための呼吸筋のトレーニングを行います。腹式呼吸を練習することで、呼吸機能を高め、誤って気管に食べ物や飲み物が入ってしまった際、排出しやすくします。
発声訓練
「パ・タ・カ・ラ」の音を大きな声で繰り返すことで、食べるために必要な筋肉を鍛え、嚥下に関わる器官の動きを活性化します。日常の会話やカラオケも効果的です。
直接訓練
直接訓練では、実際に食べ物を使って嚥下の能力を向上させます。
食品の調整
嚥下の状態に応じて、食べ物の形状や柔らかさを調整します。例えば、とろみ調整食品やミキサーにかけた食品を使うことで、飲み込みやすい食事にします。
交互嚥下
ぱさつきやべたつきの強い食べ物とゼラチンゼリーや水(とろみ水)を交互に摂取することで、飲み込みやすくし、食べ物が口の中やのどに残るのを防ぎます。
複数回嚥下
食事一口につき2回以上飲み込むことで、口の中や咽頭に食べ物が残らないようにします。
1回量の調整
1口の量が多いと口の中や咽頭に食べ物が残り、誤嚥や窒息するリスクが高くなります。食具の調整や1口の量を調整していきます。
姿勢調整
体や首の位置などの姿勢は食べる機能に大きな影響を及ぼします。飲み込みの状態に合わせた姿勢を調整することで、誤嚥しにくく食べやすい姿勢をとるようにします。
手術
手術は、嚥下機能の改善を目的とする手術と誤嚥防止術に大きく分けられます。当院では、手術が検討される場合は、連携する医療機関をご紹介いたします。
嚥下機能改善手術
誤嚥をできるだけ減らし、口からの食事を可能にすることを目指します。手術後にはリハビリが不可欠であり、嚥下機能の回復が見られない場合には、さらに別の手術が必要になることがあります。
誤嚥防止術
嚥下機能改善手術の結果が不十分な場合、食道と気道を分けるための手術が行われることがあります。食べ物や液体が気道に入ることを防ぐためのものですが、声を失うリスクがあるため、慎重に判断する必要があります。