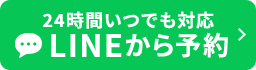「血小板が多い」と指摘された方へ
 血小板が増加している状態は「血小板増加症」と呼ばれ、血液検査で血小板数が通常の基準範囲である15万〜45万/μLを超えることを指します。血小板数が増える理由として、体が出血を防ぐために反応している場合や、骨髄に異常が生じていることが考えられます。血小板は出血時には血を固める役割を果たしますが、過剰に増加すると血栓のリスクが高まります。
血小板が増加している状態は「血小板増加症」と呼ばれ、血液検査で血小板数が通常の基準範囲である15万〜45万/μLを超えることを指します。血小板数が増える理由として、体が出血を防ぐために反応している場合や、骨髄に異常が生じていることが考えられます。血小板は出血時には血を固める役割を果たしますが、過剰に増加すると血栓のリスクが高まります。
血小板増加症の原因は大きく分けて一次性と二次性に分類されます。一次性の場合は骨髄の異常が原因となり、慢性骨髄性白血病、真性多血症、本能性血小板血症や原発性骨髄線維症といった骨髄増殖性腫瘍が含まれます。一方、二次性では慢性的な炎症、感染、鉄欠乏性貧血、手術後の生理的反応などが原因となることがあります。
血小板が多いのみでは無症状ですが、血栓症のリスクとなるため脳梗塞、心筋梗塞、下肢静脈血栓症、肺血栓塞栓症などを発症しやすくなります。
主な症状としまた、血小板数が100万/μlを超えるようなときは、逆に出血しやすくもなり、皮膚に青あざができたり出血が見られることもあります。診断は血液検査を行い、血小板数の測定をします。治療方法は原因に応じて異なります。高度な治療が必要な場合には、他の医療機関との連携を図ります。
「血小板が多い」ときに見られることがある症状
- 胸の痛み
- 息苦しさ
- 足の痛み
- 頭痛
- めまい
- 視力障害
など
「血小板が多い」原因となる病気
二次性血小板増加症(反応性血小板増加症)
他の病気や状況に反応して血小板が増加するものです。炎症や感染、手術後、鉄欠乏症、悪性腫瘍などが原因となります。血小板数が高くなることで血栓形成のリスクが増すことがありますが、通常は根本的な原因を治療することで血小板数は正常に戻ります。診断は血液検査によって行い、治療は原因疾患に応じて実施されます。
本能性血小板血症
本能性血小板血症は、血小板が異常に増加する病気で、白血球、赤血球の増加も伴うことがあります。骨髄の異常が原因です。血小板が多いことで、心筋梗塞や脳梗塞など血栓症のリスクが増えます。100万/μlを超えるような高度の血小板増多の場合は、逆に出血のリスクが増えることがあり注意が必要です。診断は血液検査で血小板の上昇を確認し、JAK2遺伝子変異の検査、骨髄検査も行います。治療はアスピリンなどの抗血小板薬、ヒドロキシカルバミドという抗がん剤やアナグレリドなどの薬物療法で血小板数を減らすことが中心で、血栓症の予防が重視されます。ヒドロキシカルバミドは抗がん剤ではありますが、吐き気や脱毛はほぼ起こりません。皮膚潰瘍など皮膚の症状が出現することがあり注意が必要です。
また、一部の患者さんで骨髄線維症、白血病へ移行することもあり定期的な受診が必須となります。
慢性骨髄性白血病
慢性骨髄性白血病は、骨髄内で異常な造血幹細胞が増殖し、白血球が過剰に増加する血液疾患です。血小板増多、貧血を伴うことがあります。主にフィラデルフィア染色体(BCR-ABL融合遺伝子)の異常によって引き起こされます。初期には無症状で健診を契機にみつかることの多い病気です。進行すると疲労感や体重減少、発熱、脾臓の腫れなどの症状が見られます。治療にはイマチニブ、ダサチニブなどのチロシンキナーゼ阻害薬が非常に有効で、健常者と同等の予後が期待できます。しかし、進行し急性白血病へ転化することがあり、その際は抗がん剤治療、骨髄移植などの造血幹細胞移植が検討されます。
原発性骨髄線維症
原発性骨髄線維症は、骨髄内に線維組織が増殖し、正常な造血機能が阻害される病気です。JAK2遺伝子の変異が関連していることが多く、白血球・血小板増多、貧血となり、脾臓の腫れ、体重減少、発熱などの症状が現れます。診断には血液検査、JAK2遺伝子変異の検査、骨髄検査での骨髄線維化の確認が必要です。無症状の場合は無治療経過観察のこともあります。治療にはJAK2阻害剤、高リスク例では骨髄移植などの造血幹細胞移植が考慮されます。
真性多血症
真性多血症は、骨髄で赤血球が異常に増加する病気で、これにより血液がドロドロになり、心筋梗塞や脳梗塞などの血栓症のリスクが高まります。白血球、血小板の増加も伴うことがあります。主な原因はJAK2遺伝子の変異であることが多いです。症状としては、頭痛、めまい、かゆみ、血栓による痛み、皮膚の紅潮などが見られます。診断は血液検査で赤血球数やヘモグロビンの上昇を確認し、JAK2遺伝子変異の検査、骨髄検査も行います。治療は瀉血(血液を抜きとる処置)やアスピリンなどの抗血小板薬、ヒドロキシカルバミドという抗がん剤で赤血球数を減らすことが中心で、血栓症の予防が重視されます。ヒドロキシカルバミドは抗がん剤ではありますが、吐き気や脱毛はほぼ起こりません。皮膚潰瘍など皮膚の症状が出現することがあり注意が必要です。また、一部の患者さんで骨髄線維症、白血病へ移行することもあり定期的な受診が必須となります。
「血小板が多い」に関するよくある質問
血小板が多いとどのような合併症が起こる可能性がありますか?
血小板が多いことで、血栓が形成されやすくなり、心筋梗塞や脳梗塞、肺塞栓症などの重篤な合併症を引き起こすリスクが高まります。また、慢性的に血小板が多い状態が続くと、動脈硬化が進行することがあります。
血小板が多い場合、飲酒はどう影響しますか?
飲酒は血小板の機能に影響を与えることがあります。特に大量に飲酒すると、血小板の機能が低下し、出血傾向が強まる可能性があります。医師と相談し、適切な飲酒量を守ることが推奨されます。
血小板が多い場合、どのような食事が推奨されますか?
血小板数が多いことは、動脈硬化が進行し脳卒中や心筋梗塞のリスクになります。生活習慣病の管理と共に、果物や野菜、全粒穀物、良質な蛋白質を豊富に含むバランスの取れた食事が重要です。また、オメガ-3脂肪酸を含む食品(魚、ナッツなど)や抗炎症作用のある食品を摂取することも推奨されます。
ストレスで血小板が多くなることはありますか?
ストレスは身体のさまざまな生理的反応を引き起こし、血小板の増加に寄与する可能性があります。ストレスが慢性的であれば、体内の炎症反応が強まり、血小板数が増加することがあるため、ストレス管理が重要です。
血小板数の増加は一時的なものでしょうか?
血小板数の増加は一時的な場合もあります。感染症や外傷など、体が一時的に反応している場合、血小板数が増加することがあります。ただし、持続的に高い数値が続く場合は、医師の診断と治療が必要です。
血小板が多いと運動に制限があるのですか?
血小板が多い場合、特別に運動の制限はありません。ただ、血小板が多いことは血栓症のリスクが高くなるので、脱水には注意が必要です。運動時は適度な水分摂取を意識しましょう。
また、血液検査で血小板数が100万/μlを超えるときは、出血しやすくなることがありますので、高強度の運動や衝撃の強い運動は控えたほうが良いでしょう。どれくらいまで運動を行って良いか、医師に相談してみましょう。
血小板の数が多いことは妊娠に影響しますか?
血小板数が多いと妊娠に影響を与える可能性があります。妊娠中は血液が固まりやすくなるため、特に血栓症のリスクが高まります。妊娠を計画している場合は、医師に相談し、適切な管理を行うことが重要です。