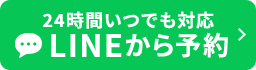- 「血液検査で蛋白が多い」と指摘された方へ
- 「血液検査で蛋白が多い(M蛋白)」ときに見られることがある症状
- 「血液検査で蛋白が多い(M蛋白)」原因となる病気
- 「血液検査で蛋白が多い(M蛋白)」に関するよくある質問
「血液検査で蛋白が多い」と指摘された方へ
 血液検査で蛋白が多いと指摘された場合、「M(モノクローナル)蛋白」が体の中にある場合があります。M蛋白は特定の異常な抗体(IgG、IgA、IgMなど)で、主に異常な形質細胞(抗体をつくる細胞)によって生成されます。血液中の総蛋白量は6.0〜8.0g/dL程度が基準とされており、M蛋白が増えると、この正常範囲を超えることがあります。
血液検査で蛋白が多いと指摘された場合、「M(モノクローナル)蛋白」が体の中にある場合があります。M蛋白は特定の異常な抗体(IgG、IgA、IgMなど)で、主に異常な形質細胞(抗体をつくる細胞)によって生成されます。血液中の総蛋白量は6.0〜8.0g/dL程度が基準とされており、M蛋白が増えると、この正常範囲を超えることがあります。
M蛋白が高い状態は、特に多発性骨髄腫や原発性マクログロブリン血症などの病状と関連しています。これらの病気では、骨髄内の形質細胞が異常に増殖し、過剰な蛋白が作られるため、結果的に血液中のM蛋白が増加します。
多発性骨髄腫の症状としては、疲労感、体重減少、骨の痛み、高カルシウム血症、貧血、腎機能の低下、そして感染症のリスク増加が見られることがあります。原発性マクログロブリン血症はリンパの腫れや貧血を認め、血液中の粘度が上がることで循環障害を引き起こし、慢性的な疲労、視力障害や頭痛、めまいなどの神経症状、血栓症が現れることもあります(過粘調度症候群)。
M蛋白を検出するためには、血清電気泳動検査や免疫固定法が用いられます。M蛋白が検出されたら、M蛋白の原因診断のため骨髄検査を行うことがあります。診断が確定した後にはCTやMRIなどの画像診断が行われます。多発性骨髄腫や原発性マクログロブリン血症は、無治療経過観察のこともありますが、治療が必要な際には分子標的薬や免疫調節薬、抗がん剤や放射線療法が必要になることもありますので、早めに医師に相談することが重要です。
「血液検査で蛋白が多い(M蛋白)」ときに見られることがある症状
「血液検査で蛋白が多い(M蛋白)」原因となる病気
多発性骨髄腫
多発性骨髄腫は、腫瘍化した形質細胞が異常なM蛋白を生成する病気です。原因は明らかではありませんが、特に高齢者に多く見られます。主な症状には、骨の痛み、貧血、頻繁な感染、腎機能の低下、高カルシウム血症などが含まれます。診断は血液検査や骨髄検査を通じて行われ、症状がない場合(くすぶり型)は無治療経過観察となりますが、治療が必要な際は分子標的薬や免疫調節薬、抗がん剤、放射線療法が行われます。比較的若年の方には自家末梢血幹細胞移植も行われます。高度な検査や治療が必要な際は、連携する医療機関をご紹介します。
原発性マクログロブリン血症・リンパ形質細胞性リンパ腫
原発性マクログロブリン血症・リンパ形質細胞性リンパ腫は悪性リンパ腫の一つで、B細胞から形質細胞になりかけのリンパ形質細胞のがん化により発症する病気です。特に異常なIgMをたくさん作る場合、原発性マクログロブリン血症といいます。リンパの腫れや貧血を認め、血液中の粘度が上がることで循環障害を引き起こし、慢性的な疲労、視力障害や頭痛、めまいなどの神経症状、血栓症が現れることもあります(過粘調度症候群)。診断は血液検査や骨髄検査、リンパ節生検によって行われます。無症状の場合は無治療経過観察となりますが、治療が必要な際は分子標的薬や抗がん剤が使用されます。過粘調度症候群がある場合は、血漿交換が検討されます。必要に応じて、高度な検査や治療を提供する医療機関を紹介します。
MGUS(意義不明の単クローン性免疫グロブリン血症)
MGUSは、M蛋白が増加しているものの特に症状を伴わず、M蛋白の値もそれほど高くなく、骨髄中の形質細胞の増加があまりない状態を指します。しかし、MGUSは時折、多発性骨髄腫や他の血液疾患に進展する可能性があるため、定期的な検査を医療機関で受けることが推奨されます。
「血液検査で蛋白が多い(M蛋白)」に関する
よくある質問
M蛋白の検査はどのくらいの頻度で受けるべきですか?
M蛋白の検査頻度は、年に1回の定期検査が推奨されます。症状や検査結果によっては、もっと頻繁に検査が必要な場合もあります。
M蛋白が増加することによるリスクは何ですか?
M蛋白の増加は、血液の粘度を上昇させ、血栓症や循環障害のリスクを高める可能性があります。また、多発性骨髄腫になってしまった場合は骨折、腎機能障害や感染症のリスクも増加するため注意が必要です。
M蛋白の増加が診断された場合、どのような生活習慣を心がけるべきですか?
M蛋白の増加のみ(MGUS)であれば特別に心がけることはありません。しかし、多発性骨髄腫や他の血液がんに進展する可能性があり、定期的に医師の指示に従って検査を受けることが大切です。
M蛋白の状態が長期間続くと、どのような影響がありますか?
M蛋白があるのみで、それ程多くなければ問題ありません。ただ、M蛋白が長期間増加している場合、血液の粘度が高まり、心血管系の問題や腎機能障害が進行する可能性があります。医師と相談のうえ、定期的な診察、検査が必要です。
M蛋白の増加は遺伝的要因によるものですか?
原因は明らかにされていませんが、現時点では遺伝する病気でないとされています。年齢とともに、M蛋白を認める割合が増えてきます。
M蛋白が増加しているが症状がない場合、治療は必要ですか?
M蛋白が増加していても無症状の場合、必ずしも治療が必要というわけではありません。しかし、多発性骨髄腫や他の血液がんに進展する可能性があり、医師と相談のうえ、定期的な診察、検査が必要です。
M蛋白の増加があると日常生活にどのような影響がありますか?
M蛋白の増加がある場合、場合によっては疲労感や身体のだるさを感じることがありますが、無症状の場合は日常生活に大きな影響がないこともあります。
M蛋白が高い場合、食事に気をつけるべきことはありますか
M蛋白が高い場合は、特別に気を付ける必要はありません。ただ、M蛋白の値が非常に高い方は脳梗塞や心筋梗塞などの血栓症のリスクとなります。水分摂取をしっかり行い脱水を予防するとともに、生活習慣病の管理と栄養バランスの取れた食事を心がけることが重要です。