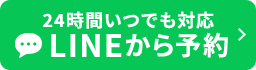「白血球が多い」と指摘された方へ
 「白血球が多い」と診断される状態は、医学的には「白血球増加症」と言います。白血球は免疫システムの一環として、感染や炎症に対する防御で重要な役割を果たしています。成人の場合、通常の白血球数は血液検査で約3,500~9,000個/μlで、この範囲を超えると異常とされます。白血球増加の原因はさまざまで、感染症や炎症、肥満、喫煙、ストレス、アレルギー反応、悪性腫瘍などが挙げられます。
「白血球が多い」と診断される状態は、医学的には「白血球増加症」と言います。白血球は免疫システムの一環として、感染や炎症に対する防御で重要な役割を果たしています。成人の場合、通常の白血球数は血液検査で約3,500~9,000個/μlで、この範囲を超えると異常とされます。白血球増加の原因はさまざまで、感染症や炎症、肥満、喫煙、ストレス、アレルギー反応、悪性腫瘍などが挙げられます。
症状は基礎疾患によって異なりますが、感染症の場合は発熱、疲労感、発汗、寒気などが見られることがあります。また、白血球が過剰に増加すると、病気によっては血液中の他の成分とのバランスが崩れ、疲労、頭痛、息切れ、出血しやすくなるといった症状が現れることもあります。特に慢性的に白血球が多い状態が続く場合、白血病などの重篤な疾患の可能性も考えられます。そのため、健康診断や検査で白血球の増加が指摘された際には、血液内科専門医の診察を受けることをお勧めします。当院でも診療を行っておりますので、どうぞご相談ください。
「白血球が多い」ときに見られることがある症状
「白血球が多い」原因となる病気
感染症
細菌が引き起こす感染症は、白血球の増加を招くよくある原因です。体が免疫反応を強化するために白血球を増やし、発熱や咳、下痢などの症状が現れます。診断は血液検査や病原体検査で行い、治療は原因となる感染に応じて抗生物質が処方されます。
アレルギー反応
アレルギー反応やアナフィラキシーでは、特定の白血球(好酸球)が増加します。これはアレルゲンに対する体の過剰反応が原因で、皮膚のかゆみ、発疹、呼吸困難などが見られます。白血球の増加は血液検査で確認され、治療は抗ヒスタミン薬やステロイドの使用が一般的です。
ストレス
ストレスや脱水が原因で、白血球が増加することがあります。体がストレスに反応し、疲労感や頭痛、息切れなどの症状を引き起こします。血液検査で白血球数の増加が確認され、治療にはストレスの軽減が中心となります。
喫煙
たばこに含まれる有害物質によって、体が慢性的に炎症を起こし、白血球が増加します。 喫煙は心筋梗塞や脳梗塞のリスクになりますが、白血球が増加することでさらにリスクが高まります。禁煙することが重要です。
自己免疫疾患
自己免疫疾患では、免疫系が自らの細胞を攻撃するため、白血球が増加することがあります。例えば、関節リウマチや多発性筋炎・皮膚筋炎などの病気が該当し、症状は、関節の痛みや皮膚の発疹、筋肉に痛みなど多岐にわたります。診断には血液検査や免疫学的検査が必要で、治療には免疫抑制剤が使われることが多いです。
骨髄異形成症候群
骨髄(血液の工場)にある、血液細胞の元となる造血幹細胞の異常が原因となる病気です。血液細胞の不良品を作り、赤血球、白血球、血小板が正常に作られなくなります。抗がん剤治療や放射線被曝がリスク要因とされています。白血球は減少することが多いですが、正常もしくは増加することもあります。症状には貧血による疲労感や皮膚のあざや出血、感染リスクの増加があります。診断には骨髄穿刺が必要です。治療は、低リスクの場合は無治療経過観察や輸血、エリスロポエチン製剤の注射を投与することがあります。高リスクの場合は、アザシチジンという抗がん剤の投与や、骨髄移植などの造血幹細胞移植が考慮されます。
慢性骨髄性白血病
慢性骨髄性白血病は、骨髄内で異常な造血幹細胞が増殖し、白血球が過剰に増加する血液疾患です。主にフィラデルフィア染色体の異常によって引き起こされます。初期には無症状で健診を契機にみつかることの多い病気です。進行すると疲労感や体重減少、発熱、脾臓の腫れなどの症状が見られます。治療にはチロシンキナーゼ阻害剤という分子標的薬が非常に有効で、健常人とほぼ同等の予後が期待できるようになりました。しかし、進行すると急性白血病へ移行することがあり、その際は抗がん剤治療、骨髄移植などの造血幹細胞移植が検討されます。
急性白血病
急性白血病は、未熟な白血球が「がん化」し、異常に増殖する病気です。主に、急性骨髄性白血病と急性リンパ性白血病にわけられます。原因は明らかではありませんが、放射線や抗がん剤、化学物質への暴露などが関与することがあります。まれに、遺伝的な要因があることも知られています。発熱や疲労感、貧血、出血傾向などの症状が現れ、診断には血液検査や骨髄検査が必要です。治療には抗がん剤治療が主に行われ、必要に応じて骨髄移植などの造血幹細胞移植も検討されます。この病気が疑われた場合は、早急な治療が必要なため連携する医療機関に紹介いたします。
慢性リンパ性白血病
白血球に含まれる成分にリンパ球があります。リンパ球のうちB細胞が異常に増加する慢性リンパ性白血病は、進行が緩やかな血液疾患です。日本人には少なく、白人に多い白血病です。初期には無症状で健診を契機にみつかることの多い病気です。進行すると疲労感やリンパ節の腫れ、発熱などが見られます。診断には血液検査や骨髄検査が行われ、状態によっては無治療経過観察のことも多いです。治療が必要な場合は分子標的薬や抗がん剤が選択されます。
原発性骨髄線維症
原発性骨髄線維症は、骨髄内に線維組織が増殖し、正常な造血機能が阻害される病気です。JAK2遺伝子の変異が関連していることが多く、貧血や脾臓の腫れ、体重減少、発熱などの症状が現れます。診断には血液検査、JAK2遺伝子変異の検査、骨髄検査での骨髄線維化の確認が必要です。無症状の場合は無治療経過観察のこともあります。治療にはJAK2阻害剤、高リスク例では骨髄移植などの造血幹細胞移植が考慮されます。
真性多血症
真性多血症は、骨髄で赤血球が異常に増加する病気で、これにより血液が濃くなり、心筋梗塞や脳梗塞など血栓症のリスクが高まります。白血球、血小板の増加も伴うことがあります。主な原因はJAK2遺伝子の変異であることが多いです。症状としては、頭痛、めまい、かゆみ、血栓による痛み、皮膚の紅潮などが見られます。診断は血液検査で赤血球数やヘモグロビンの上昇を確認し、JAK2遺伝子変異の検査、骨髄検査も行います。治療は瀉血やアスピリンなどの抗血小板薬、ヒドロキシカルバミドという抗がん剤で赤血球数を減らすことが中心で、血栓症の予防が重視されます。ヒドロキシカルバミドは抗がん剤ではありますが、吐き気や脱毛はほぼ起こりません。皮膚潰瘍など皮膚の症状が出現することがあり注意が必要です。
また、一部の患者さんで骨髄線維症、白血病へ移行することもあり定期的な受診が必須となります。
本態性血小板血症
本熊血小板血症は、血小板が異常に増加する病気で、白血球、赤血球の増加も伴うことがあります。骨髄の異常が原因です。血小板が多いことで心筋梗塞や脳梗塞などの血栓症のリスクが増えます。100万/μlを超えるような高度の血小板増多の場合は、逆に出血のリスクが増えることがあり注意が必要です。診断は血液検査で血小板の上昇を確認し、JAK2遺伝子変異の検査、骨髄検査も行います。治療はアスピリンなどの抗血小板薬、ヒドロキシカルバミドという抗がん剤やアナグレリドなどの薬物療法で血小板数を減らすことが中心で、血栓症の予防が重視されます。ヒドロキシカルバミドは抗がん剤ではありますが、吐き気や脱毛はほぼ起こりません。皮膚潰瘍など皮膚の症状が出現することがあり注意が必要です。また、一部の患者さんで骨髄線維症、白血病へ移行することもあり定期的な受診が必須となります。
「白血球が多い」に関するよくある質問
白血球が多いと「がん」のリスクが高まりますか?
白血球増加そのものが「がん」を直接的に示すわけではありませんが、慢性的な白血球増加は、白血病などの血液のがんと関連する場合があります。長期間白血球が増加している場合や、他の異常がある場合には、追加の検査や専門医の診察を受けることが推奨されます。
白血球が多いと再検査が必要ですか?
白血球数が一時的に増加することは珍しくありませんが、原因が明らかでない場合や、症状が続く場合には再検査が必要です。特に、数値が異常に高い場合や、他の血液検査の結果に異常がある場合は、血液内科での精密検査が推奨されます。
白血球が多いことは遺伝的な要因がありますか?
稀に、白血球増加症は遺伝的な要因が影響することがあります。特に、骨髄の異常による血液疾患においては、家族に同様の病歴がある場合、リスクが高まることがあります。しかし、白血球の増加自体は多くの場合、感染症やストレスなどの環境要因によるものです。
妊娠中に白血球が増加することはありますか?
妊娠中はホルモンの変化や体内のストレスにより、白血球数が増加することがよくあります。これは、通常の生理的な反応とされ、特に妊娠後期に見られることがあります。妊娠中の白血球増加が心配な場合は、医師に相談することが重要です。
白血球が多いと食生活に影響がありますか?
白血球が多いこと自体が、食生活に影響をあたえることはありません。ただ、肥満で白血球が多くなることがあります。その際は、バランスの取れた食事を心掛け、生活習慣の改善が重要です。
白血球が多いことが心理的な要因に関係することはありますか?
ストレスや心理的な負荷が免疫系に影響を与えることがあるため、白血球が増加することがあります。心の健康を保つことは、体全体の健康に寄与するため、リラクゼーションやストレス管理が重要です。
白血球が多い場合、食事に気を付けるべきことはありますか?
特別に気を付けることはありません。ただ、肥満により白血球が多くなることがあります。その際はバランスの取れた食事を心掛け、生活習慣の改善が重要です。