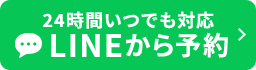高血圧
 高血圧とは、血液が血管内を流れる際に、血管壁にかかる圧力が常に高い状態を指します。血圧は心臓が血液を送り出し収縮する際の「収縮期血圧」と、心臓が拡張する際の「拡張期血圧」の2つの値で表され、正常値は収縮期が120mmHg未満、拡張期が80mmHg未満です。高血圧は、収縮期血圧が140mmHg以上、または拡張期血圧が90mmHg以上の場合を指します。これらは健診や医療機関で測定した際の基準値で、自宅で測定した場合は、それぞれ5mmHg低い値が基準になります(例えば、高血圧の基準は135/85mmHg以上)。高血圧は、心臓病や脳卒中、腎臓病などの重大な疾患のリスクを高めるため、早期の発見と適切な管理が重要です。
高血圧とは、血液が血管内を流れる際に、血管壁にかかる圧力が常に高い状態を指します。血圧は心臓が血液を送り出し収縮する際の「収縮期血圧」と、心臓が拡張する際の「拡張期血圧」の2つの値で表され、正常値は収縮期が120mmHg未満、拡張期が80mmHg未満です。高血圧は、収縮期血圧が140mmHg以上、または拡張期血圧が90mmHg以上の場合を指します。これらは健診や医療機関で測定した際の基準値で、自宅で測定した場合は、それぞれ5mmHg低い値が基準になります(例えば、高血圧の基準は135/85mmHg以上)。高血圧は、心臓病や脳卒中、腎臓病などの重大な疾患のリスクを高めるため、早期の発見と適切な管理が重要です。
高血圧の原因
高血圧の原因は、主に2つに分類されます。1つは「本態性高血圧」で、遺伝的要因や年齢、食生活、運動不足、ストレスなどが関与し、全体の90%以上を占めます。もう1つは「二次性高血圧」で、腎臓病やホルモン異常など特定の疾患が原因で発生します。10人に1人程度が二次性高血圧であるといわれており、二次性高血圧の患者さんでも、本態性高血圧として治療されていることもあります。必要に応じて、ホルモン検査などを行い、二次性高血圧を除外することも大事です。塩分の過剰摂取や肥満、喫煙、アルコールの過剰摂取などの生活習慣が、高血圧を引き起こす大きな要因となります。
高血圧の症状
高血圧は「サイレントキラー」と呼ばれることが多く、初期には自覚症状がほとんどないことが一般的です。しかし、高血圧の状態が長く続いたり、著しく血圧が上がった場合は頭痛、めまい、耳鳴り、動悸、視力障害などの症状が現れることがあります。長期間放置すると、心臓や腎臓、脳などの臓器にダメージを与え、動脈硬化や心筋梗塞、脳卒中、腎不全などの重篤な合併症を引き起こすリスクが高まります。
高血圧の治療方法
高血圧の治療は、主に生活習慣の改善と薬物療法によって行われます。生活習慣の改善には、塩分を控えた食事、適度な運動、禁煙、節酒、ストレス管理が含まれます。また、肥満がある場合は、減量も有効です。
一般的に75歳未満であれば、血圧 130/80mmHg未満(家庭血圧 125/75mmHg)を目指し、75歳以上では血圧 140/90mmHg未満(家庭血圧 135/85mmHg)を目指しますが、持病の状態で目標が変わることがあります。
自宅でも毎日血圧を測定し、記録に残すことも大切です。
薬物療法としては、下記の薬剤が使用されます。
高血圧に使用する薬剤
カルシウム拮抗薬
多くの患者さんに使用されている安全な薬剤で、血管を拡張させ、血圧を低下させる作用があります。
副作用として、むくみが見られることがあります。
また、稀ではありますが歯肉腫脹の原因となる薬剤です。
グレープフルーツなどの柑橘類との相互作用に注意が必要で、薬が効きすぎてしまうことがあります。
アンギオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)、アンギオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬
これらの薬剤も多くの患者さんに使用されている薬剤です。ARBはアンギオテンシンⅡという血管を収縮させるホルモンが作用しにくくすることで、血管を拡張させる薬剤です。一方、ACE阻害剤はアンギオテンシンⅡをつくる酵素であるACEを阻害し、血管を拡張させます。心臓や腎臓を保護する作用もあります。副作用として、血液のミネラルバランスの異常や腎機能に影響を及ぼすことがあります。また、ACE阻害薬の副作用で、空咳がでることがあります。
アンギオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬(ARNI)
上記のARBに加え、ネプリライシン阻害作用がある薬剤で、新しいタイプの薬剤です。ネプリライシンとは血管を広げるホルモンや、心保護作用のあるナトリウム利尿ペプチドを抑制してしまう作用があります。ARBに加え、このネプリライシンを抑えることで、血圧を下げる効果があります。
サイアザイト系またはサイアザイド類似利尿剤
腎臓に作用し、水分、塩分を尿として排出することで、血圧を下げる作用があります。塩分を摂り過ぎの方に特に有効です。歴史が長く、安価でもあります。副作用として、血液のミネラルバランスの異常や腎機能に影響を及ぼすことがあります。また、尿酸値や血糖値を上げることもあります。
ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬
アルドステロンというホルモンの働きを抑える薬剤です。アルドステロンは水、塩分を体の中に保つ作用があります。水、塩分が体にたまると血圧は上昇しますが、このホルモンを抑えることで、血圧が低下します。心臓を保護する作用もあります。古い薬剤ではスピロノラクトンという薬剤がありますが、男性の場合、女性化乳房という副作用が出現することがあります。また、血液のミネラルバランスの異常をきたすことがあります。最近は、効果が高く副作用の少ない新しい薬剤が登場しています。
β遮断薬
心臓の筋肉に作用し交感神経のβ1受容体を遮断することで、心拍数を下げ心臓の収縮を調整し、血圧を低下させます。脈拍が早い方に効果的です。慢性心不全の患者さんの予後を改善する効果もあります。副作用として、喘息や糖尿病を悪化させる可能性があり注意が必要です。
α遮断薬
交感神経のα1受容体を遮断し、血管を拡張させることで血圧が低下します。交感神経が優位になる朝に血圧が高い方に有効です。めまいやふらつきが出ることがありますが、少量より開始することで安全に投与できます。
高血圧の予防
高血圧の予防には、生活習慣の見直しが重要です。塩分摂取を控え、野菜や果物を多く含むバランスの取れた食事を心がけましょう。また、適度な運動を日常に取り入れることで、血圧を安定させる効果があります。さらに、喫煙や過度な飲酒を避けることも、予防に大きく寄与します。ストレスの管理も重要で、リラクゼーションや趣味の時間を持つことが効果的です。
脂質異常症
脂質異常症とは、血液中の脂質(コレステロールや中性脂肪)のバランスが崩れる状態を指します。具体的には、悪玉コレステロール(LDLコレステロール)が増加、善玉コレステロール(HDLコレステロール)が減少、中性脂肪が増えることを指します。動脈硬化を進行させ、心筋梗塞や脳卒中などの心血管疾患のリスクを高めます。症状がないことが多いため、定期的な血液検査で早期発見が重要です。
LDLコレステロール140mg/dl以上、HDLコレステロール 40mg/dl未満、Non-HDLコレステロール 170mg/dl以上、空腹時中性脂肪 150mg/dl以上(非空腹時 175mg/dl以上)のいずれかで、脂質異常症と診断されます。
Non-HDLコレステロールとは、LDLコレステロール以外の悪玉コレステロール(リポタンパクやレムナント)も含めた指標となります。
脂質異常症の原因
脂質異常症の原因は、主に遺伝的要因と生活習慣によるものに分かれます。遺伝的要因としては、家族性高コレステロール血症などが挙げられます。一方、生活習慣では、食事の影響が大きく、高脂肪食や糖分の多い食事、運動不足、肥満、喫煙、過度な飲酒が脂質異常を引き起こす要因です。また、糖尿病や甲状腺機能低下症などの基礎疾患も脂質異常を招くことがあります。
脂質異常症の症状
脂質異常症は、初期には特に自覚症状がないため「サイレントキラー」とも呼ばれます。自覚症状が出ないまま動脈硬化が進行し、心筋梗塞や脳卒中などの重大な合併症を引き起こすことがあります。まれに、瞼の内側の皮膚やアキレス腱などに黄色腫(コレステロールが沈着したこぶのようなもの)ができることがあります。
脂質異常症の治療方法
脂質異常症の治療は、生活習慣の改善と薬物療法が中心です。生活習慣改善には、脂肪や糖質を控えた食事、適度な運動、禁煙、節酒が重要です。食事療法では、魚や野菜、食物繊維を多く摂取し、飽和脂肪酸の多い食品を避けることが推奨されます。薬物療法では、スタチンやフィブラート系薬剤などが使用され、LDLコレステロールや中性脂肪の低下を目指します。治療目標値は中性脂肪 150mg/dl未満、HDLコレステロール 40mg/dl以上ですが、LDLコレステロールに関しては、患者さんの状況により目標値がかわります。
「喫煙」、「高血圧」、「低HDLコレステロール」、「耐糖能異常」、「若くして冠動脈疾患になった家族歴」を危険因子とし、危険因子の数や年齢、性別によりリスク分類されます。低リスク LDLコレステロール160mg/dl未満、中リスク140mg/dl未満、高リスク120mg/dl未満が目標となります。さらに、下記のような合併症がある方は、より厳格にLDLコレステロール値をコントロールする必要があります。
| 項目 | LDLコレステロールの目標値 |
|---|---|
| 家族性コレステロール血症の方 |
100mg/dl未満 |
| 「冠動脈疾患(狭心症や心筋梗塞など)」や「アテローム血栓性脳梗塞」の既往がある方 |
100mg/dl未満 |
|
冠動脈疾患又はアテローム血栓性脳梗塞に加え、「急性冠症候群」、「家族性高コレステロール血症」、「糖尿病」のいずれかがある方、「冠動脈疾患」+「アテローム血栓性脳梗塞」のある方 |
70mg/dl未満 |
| 「糖尿病」、「慢性腎臓病」、「末梢動脈疾患」のいずれかがある方 |
120mg/dl未満 |
| 糖尿病に加え、「網膜症・腎症・神経障害」を合併していたり、「末梢動脈疾患」、「喫煙」のいずれかががある方 |
100mg/dl未満 |
脂質異常症で使用される主な薬剤は下記です。
脂質異常症で使用する薬剤
スタチン系
効果的で最もよく使用される薬剤です。肝臓でのコレステロール合成にかかわる酵素を阻害することで、血液中のコレステロール(主にLDLコレステロール)を低下させます。
LDLコレステロール低下の度合いによって、ストロングスタチンとスタンダードスタチンに分けられます。副作用として、足のつりや筋肉痛などが出現することがあります。稀に、横紋筋融解症といって筋肉が壊れ、壊れたときに発生する物質が腎臓を障害し腎不全となることもあります。非常に強い筋肉痛や脱力などが出現した場合は、すぐに医療機関を受診する必要があります。
フィブラート系
肝臓でのコレステロールや中性脂肪の合成を阻害する作用があります。また、中性脂肪の分解を促進させ、血中の中性脂肪を低下させます。主に中性脂肪を下げる目的で使用されます。副作用に関してはスタチン系と同様のものが多いです。
小腸コレステロールトランスポーター阻害剤
小腸でのコレステロール吸収を抑制することで、血液中のコレステロールを低下させます。スタチンで効果が不十分な場合などに併用して使用されることが多い薬剤です。
イコサペント酸エチル(EPA)製剤、オメガ-3脂肪酸エチル(EPA + DHA)
魚の油が原材料になっている薬剤です。肝臓での中性脂肪合成を抑制し、血液中の中性脂肪を低下させる作用があります。抗血小板作用(血小板の機能を抑える)があり、手術などの出血するような処置を行う際は注意が必要です。
PCSK9標的薬
この薬剤は新しい薬剤で強力な作用があります。しかし、高価であることや、現時点では注射剤しかないことが欠点です。スタチンを併用するか、スタチンが副作用で使用できない場合に投与が検討されます。PCSK9とは血液中のLDLコレステロールの増加因子です。このPCSK9を標的することで血液中から肝臓へのLDLコレステロール取り込みを促し、血中のLDLコレステロールを下げる作用があります。
脂質異常症の予防
脂質異常症の予防には、バランスの良い食生活と運動習慣が不可欠です。特に、飽和脂肪酸を多く含む食品(肉類やバター)を控え、魚や大豆製品、野菜、果物を積極的に摂取しましょう。また、運動を日常生活に取り入れ、週に数回の有酸素運動を行うことが効果的です。喫煙や過度なアルコール摂取を避け、体重管理も予防に大きく影響します。
糖尿病
糖尿病は、血糖値が慢性的に高くなる代謝疾患で、インスリンの分泌や作用に問題が生じることが原因です。糖尿病は、「1型糖尿病」、「2型糖尿病」、「その他の原因による糖尿病」、「妊娠糖尿病」の4種類に分かれます。1型糖尿病は自己免疫の問題でインスリンがほとんど生成されなくなる疾患で、若年層に多いです。2型糖尿病は中高年層に多く、インスリンの作用が低下することで血糖値が上がるものです。長期間高血糖状態が続くと、血管や神経にダメージを与え、合併症を引き起こすリスクが高まります。
糖尿病の原因
糖尿病の原因は種類によって異なります。1型糖尿病の主な原因は、自己免疫反応がインスリンを生成する膵臓のβ細胞を攻撃することで、インスリンが作れなくなることです。2型糖尿病は、遺伝的な要因に加え、不健康な食生活、運動不足、肥満、ストレスなどの生活習慣が主な原因です。また、加齢や高血圧もリスクを高めます。妊娠糖尿病は、妊娠中のホルモンの影響で一時的にインスリンの作用が低下することが原因です。
糖尿病の症状
糖尿病の初期段階では、特に自覚症状がないことが多いですが、進行すると頻尿、喉の渇き、体重減少、疲労感などの症状が現れます。さらに、血糖値の管理が不十分な状態が続くと、糖尿病の典型的な合併症である網膜症、腎症、神経障害が進行し、失明や腎不全、末端の感覚喪失につながることもあります。これらの症状が現れる前に定期的な検診で血糖値を管理することが重要です。
糖尿病の診断
糖尿病の診断は血糖値とヘモグロビンA1c(1~2か月の血糖値を反映)、糖尿病の症状(のどの渇き、多飲・多尿、体重減少)や糖尿病性網膜症の有無で下記のように診断されます
- 空腹時血糖 126mg/dl以上
- 隋時血糖 200mg/dl以上
- ブドウ糖負荷試験 2時間値 200mg/dl以上
- ヘモグロビンA1c 6.5%以上
空腹時血糖
10時間以上食事をとっていない時の血糖値です。
随時血糖
食後からの時間を問わず検査した血糖値です。
ブドウ糖負荷試験 2時間値
10時間以上食事をとっていない状態で75gの糖分を溶かした水を飲みます。その後、2時間経った時の血糖値です。
上記いずれかがあると、「糖尿病型」と診断します。この「糖尿病型」を別に日に行った検査でも確認されると「糖尿病」と診断されます。ただし、2回の検査ともに、ヘモグロビンA1cのみ基準を満たす場合は診断できません。
1回の検査のみでも「糖尿病」と診断できることもありますが、下記のいずれかの場合です。
- 糖尿病型の基準のうち、ヘモグロビンA1c 6.5%以上 に加え、血糖値のいずれの基準がある
- 血糖値が糖尿病型 + 糖尿病の症状(のどの渇き、多飲・多尿、体重減少)
- 血糖値が糖尿病型 + 糖尿病性網膜症
糖尿病の治療方法
糖尿病の治療は、病型や症状の進行具合に応じて異なります。1型糖尿病の場合、インスリン療法が必須であり、定期的にインスリン注射が必要です。2型糖尿病の治療は、食事療法、運動療法、薬物療法が中心です。食事療法では、糖質やカロリーのコントロールが重要で、運動療法は体重管理や血糖値の改善に寄与します。薬物療法には、インスリン分泌を促す薬や、インスリンの作用を強化する薬、インスリンが使用されます。
治療の目標はヘモグロビンA1cを基準に決められ、達成可能な場合は、6%未満を目指します。しかし、それが難しい場合は、糖尿病の合併症予防の目標として7%未満を目標にします。低血糖の副作用などで治療強化が困難な場合は、8%未満を目標にします。65歳以上の患者さんは、年齢、使用している薬剤、認知機能、ADL(日常生活動作)に応じて、もう少し緩い基準となります。
糖尿病の主な内服治療薬
ビグアナイド系
肝臓が糖を作ることを抑えたり、血液から筋肉への糖の取り込みを増加させる作用があります。
安価で歴史の長い薬剤であり、第一選択として使用されることも多い薬剤です。
投与開始時期に下痢や嘔気などを認めることがあります。稀ではありますが、乳酸アシドーシスという重篤な副作用があります。脱水や食事をとれないとき起こりやすく、そのような時は医師に相談が必要です。また、CT検査の際に使用する造影剤投与も、乳酸アシドーシスのリスクとなるため、造影剤投与前後の休薬が必要です。
グリミン系
新しい薬剤で、メトホルミンの重篤な副作用である乳酸アシドーシスを回避するために作られた薬剤です。メトホルミンと同様の作用を有していることに加え、血糖値に応じて膵臓からインスリンを分泌させる作用もあります。
チアゾリジン薬
肝臓が糖を作ることを抑えたり、血液から筋肉への糖の取り込みを増加させる作用があります。副作用として、むくみや体重増加あり、女性が特に起こりやすいとされています。心不全の方には使用することができません。
DPP-4阻害剤
DPP-4はインクレチンというホルモンを分解する作用があります。インクレチンは食事をとると分泌され、インスリンの分泌を促進し、血糖を上げるグルカゴンというホルモンを抑制します。したがって、DPP-4を阻害することで、インクレチンが長持ちして、血糖が下がりやすくなります。副作用として皮膚の症状が出現することがあります。また、類天疱瘡という皮膚に水疱ができる病気を合併することがあり、疑われる場合は皮膚科受診が必要です。
GLP-1受容体作動薬
比較的新しい薬剤です。GLP-1はインクレチンの一つです。インクレチンは食事をとると分泌され、インスリンの分泌を促進し、血糖を上げるグルカゴンというホルモンを抑制します。GLP-1受容体を活性化させることで、血糖値を下げる作用があります。
DPP-4阻害剤との併用はできません。
副作用として、便秘や吐き気、下痢などの消化器症状があります。注射製剤と内服薬両者があります。
SGLT2阻害剤
腎臓にある尿細管という部位から、糖が血液中に取り込まれるのを抑えます。それにより尿の中に糖を排泄し、血糖を下げます。近年、心不全や慢性腎臓病の治療薬としても使用されるようになりました。尿量が増加し脱水になることや、尿路感染症に注意が必要です。
スルホニル尿素薬
膵臓でのインスリン分泌促す薬剤です。低血糖に注意が必要です。
即効型インスリン分泌促進薬
速やかに効果があり、短時間、膵臓からのインスリン分泌を促進します。食後高血糖に有効です。低血糖に注意が必要です。
α-グルコシダーゼ阻害薬
小腸での糖の消化、吸収を抑える作用があります。食後高血糖に有効です。副作用として、お腹の張りや、下痢などが出現することがあります。
糖尿病の予防
糖尿病の予防には、バランスの取れた食生活と定期的な運動が欠かせません。特に2型糖尿病は、肥満や運動不足が原因となることが多いため、適正体重を維持することが大切です。脂肪や糖質を控え、野菜や食物繊維を多く摂取することが推奨されます。また、定期的な運動を行うことで血糖値の上昇を防ぐだけでなく、インスリンの効果を高めることができます。定期的な健康診断で血糖値の変化をチェックし、早期発見を心がけることが大切です。
高尿酸血症・痛風
 高尿酸血症とは、血液中の尿酸濃度が正常範囲を超えて高くなる状態を指し、血液検査で、尿酸が7mg/dlを超えると診断されます。尿酸は、体内でプリン体という物質が分解される過程で生成され、通常は尿を通じて排出されますが、過剰な尿酸が排出されずに蓄積すると、高尿酸血症を引き起こします。尿酸値が高くなると、結晶化した尿酸が関節に沈着し、激しい痛みを伴う痛風発作を引き起こすリスクが高まります。尿中の尿酸も多くなり、尿酸による尿路結石になりやすくなります。
高尿酸血症とは、血液中の尿酸濃度が正常範囲を超えて高くなる状態を指し、血液検査で、尿酸が7mg/dlを超えると診断されます。尿酸は、体内でプリン体という物質が分解される過程で生成され、通常は尿を通じて排出されますが、過剰な尿酸が排出されずに蓄積すると、高尿酸血症を引き起こします。尿酸値が高くなると、結晶化した尿酸が関節に沈着し、激しい痛みを伴う痛風発作を引き起こすリスクが高まります。尿中の尿酸も多くなり、尿酸による尿路結石になりやすくなります。
また、長期的に放置すると腎臓機能にも悪影響を及ぼし(痛風腎)、腎不全のリスクが増加します。
高尿酸血症の原因
高尿酸血症の主な原因は、尿酸の産生が増加するか、尿酸の排泄が低下することです。これには、食事の影響や遺伝的な要因、肥満、アルコールの過剰摂取、ストレス、運動不足などが含まれます。また、プリン体を多く含む食品(肉類、魚介類、アルコール飲料)を大量に摂取すると、尿酸値が上昇します。その他の原因として、腎機能の低下や、特定の薬物(利尿剤など)も尿酸の排泄を抑制し、高尿酸血症を悪化させることがあります。
高尿酸血症の症状
高尿酸血症自体には明確な症状がないことが多いですが、尿酸値が極端に高くなると、結晶化した尿酸が関節に沈着し、痛風発作を引き起こします。痛風は、主に足の親指の関節に激しい痛みと腫れ、赤みを伴う急性発作として現れます。これが繰り返されると、関節に損傷が蓄積し、慢性的な痛風へと進行することもあります。皮下や関節に痛風結節という「しこり」を形成することもあります。
高尿酸血症の治療方法
高尿酸血症の治療には、尿酸値を下げることが中心となります。まず、食事療法が基本であり、プリン体を多く含む食品の摂取を控え、バランスの取れた食事を心掛けます。適度な運動と体重管理も尿酸値の改善に役立ちます。薬物療法としては、尿酸の産生を抑制する薬や、尿酸の排泄を促進する薬が使用されることがあります。
痛風発作が発生した場合には、非ステロイド系抗炎症薬(NSAIDs)を用いて炎症を鎮める治療が行われます。発作の前兆を感じたらコルヒチンを服用し、発作を予防する治療もあります。
治療開始基準は合併症がない患者さんは、尿酸 9mg/dl以上です。生活習慣病や腎障害、尿路結石、虚血性心疾患などの合併症がある場合は、8mg/dl以上で治療を開始します。また、痛風発作または痛風結節がある場合は7mg/dl以上で治療を開始します。
痛風発作がでている最中は、内服治療を開始してはいけません。尿酸値が下がる時に、痛風発作が増悪する可能性があるからです。既に内服治療をしている方は、そのまま飲み続けても問題ありません。
尿酸の目標値は6mg/dl以下です。
高尿酸血症の予防
高尿酸血症を予防するためには、プリン体を多く含む食品やアルコールの摂取を控えることが重要です。また、水分を十分に摂取して尿酸の排出を促し、適度な運動を日常生活に取り入れることも効果的です。肥満は尿酸値の上昇に影響するため、体重管理も大切です。定期的な健康診断で尿酸値をチェックし、早期に高尿酸血症を発見することも予防の一環となります。