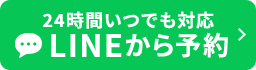「血小板が少ない」と指摘された方へ
 「血小板が少ない」ことを「血小板減少症」といいます。血小板は出血を止める役割を果たしており、正常範囲は血液検査で約15万〜45万/μlとされています。この範囲を下回ると、出血しやすくなり、内出血(あざ)ができやすくなったり、止血しにくくなったります。軽度の血小板減少では無症状であることもありますが、皮膚に小さな赤い斑点が見られる点状出血(紫斑)やあざ(紫斑)ができやすくなることが多いです。重度の場合には、鼻血や歯茎からの出血、消化管出血(便に血が混じるなど)、生理出血の増加といった症状が現れることもあります。血小板減少症の原因は多岐にわたり、特発性血小板減少性紫斑病などの自己免疫疾患、骨髄の異常、ウイルス感染などの感染症、薬剤の副作用、肝臓や脾臓の病気などが挙げられます。そのため、血小板が少ない場合は、原因を特定するために詳細な検査が必要となります。治療方法は原因によって様々になります。
「血小板が少ない」ことを「血小板減少症」といいます。血小板は出血を止める役割を果たしており、正常範囲は血液検査で約15万〜45万/μlとされています。この範囲を下回ると、出血しやすくなり、内出血(あざ)ができやすくなったり、止血しにくくなったります。軽度の血小板減少では無症状であることもありますが、皮膚に小さな赤い斑点が見られる点状出血(紫斑)やあざ(紫斑)ができやすくなることが多いです。重度の場合には、鼻血や歯茎からの出血、消化管出血(便に血が混じるなど)、生理出血の増加といった症状が現れることもあります。血小板減少症の原因は多岐にわたり、特発性血小板減少性紫斑病などの自己免疫疾患、骨髄の異常、ウイルス感染などの感染症、薬剤の副作用、肝臓や脾臓の病気などが挙げられます。そのため、血小板が少ない場合は、原因を特定するために詳細な検査が必要となります。治療方法は原因によって様々になります。
出血はどのように止まるのか?
ケガなどをして血管が破れると、フォンウィルブランド因子(血小板と傷口との接着剤にような役割)を介して、血小板が傷口に結合します。これが一次血栓(血小板血栓)というものです。
ただ、これだけでは血をとめるのに不安定であり、凝固因子という蛋白が働き、フィンブリンの網が血小板全体を覆うことで、一次血栓をより強固なものにして止血が完了します。これを二次血栓(フィブリン血栓)といいます。
あざができやすい原因は血小板が少ないこと?
あざができやすいことは、血小板が少ないこと(血小板減少症)の一つの症状として現れることがあります。血小板は血栓をつくるために重要な役割を果たしており、血管が傷ついたときに出血を止めるために必要です。血小板の数が少ないと、血液が固まりにくくなり、軽い外的刺激でも出血やあざができやすくなります。ただし、あざができやすい原因は血小板の減少だけではなく、以下のような他の要因も考えられます。
血管の脆弱性
血管が弱くなっている場合、軽い力で破れてあざができることがあります。
血液の凝固異常
血液凝固因子の異常(例えば、ビタミンK不足、血友病など)により、血液が正常に凝固できないこともあります。
薬剤の影響
アスピリンや抗凝固薬などの薬剤が血小板の機能や凝固因子に影響を与えることがあります。
したがって、あざができやすい場合は、血小板の数や凝固機能を含む詳しい検査を行うことが重要です。
「血小板が少ない」ときに見られることがある症状
- あざができやすい
- 点状出血(紫斑)が見られる
- 鼻血が頻繁に出る
- 歯茎から出血しやすい
- 生理(月経)の出血量が多い
- 生理(月経)の期間が長引く
- 血便がある
など
「血小板が少ない」原因となる病気
特発性血小板減少性紫斑病(免疫性血小板減少性紫斑病)
特発性血小板減少性紫斑病は自己の血小板に対する抗体ができてしまい、血小板を攻撃することによって血小板が減少する病気です。その原因は不明ですが、自己免疫疾患やピロリ菌が原因になることがあります。また、ウイルス感染が先行することもあります。軽度の場合は無症状のこともありますが、血小板減少が進行すると皮膚に点状出血や紫斑、鼻血、歯茎からの出血が多く見られます。血液検査で血小板数の減少を確認することに加え、他の血小板が減少する病気を除外することが重要です。必要に応じて骨髄検査で血液細胞の状態を調べます。治療方法としては、ピロリ菌が陽性の場合は除菌を行います。血小板の減少が軽度であれば無治療経過観察のこともありますが、高度の血小板減少の際はステロイドが第一選択として用いられます。ステロイドが無効であったり、副作用などで十分に投与できない場合は、トロンボポエチン受容体作動薬、リツキシマブの投与、脾臓摘出などが検討されます。
血栓性血小板減少性紫斑病
血小板が異常に減少し、同時に血栓が形成されることが特徴です。血小板が凝集して微小血管内に血栓を作り、血流を妨げます。主な原因は、ADAMTS13という酵素の活性低下です。症状は多様で、出血傾向(紫斑や点状出血)、貧血、発熱、神経症状(頭痛や意識障害)、腎機能の低下が見られます。診断は血液検査によって行われ、特に血小板数の低下と高LDH値が特徴です。治療は、血漿交換療法が中心となり、早期診断・早期治療が重要です。この病気が疑われたら、速やかに連携する医療機関へご紹介します。
再生不良性貧血
再生不良性貧血は、骨髄の造血幹細胞が正常に機能しなくなり、白血球、赤血球、血小板がすべて減少する病気です。原因は多くが不明ですが、薬剤やウイルス感染、放射線などが関係することがあります。症状は、貧血による疲労感や出血傾向、感染しやすくなることが挙げられます。治療には輸血やステロイドや免疫抑制剤、トロンボポエチン受容体作動薬の投与が行われます。重症の場合には骨髄移植などの造血幹細胞移植が検討されます。
骨髄異形成症候群
骨髄(血液の工場)にある、血液細胞の元となる造血幹細胞の異常が原因となる病気です。血液細胞の不良品を作り、赤血球、白血球、血小板が正常に作られなくなります。抗がん剤治療や放射線被曝がリスク要因とされています。赤血球、白血球、血小板はいずれも減少することが多いです。症状には貧血による疲労感や皮膚のあざや出血、感染リスクの増加があります。診断には骨髄穿刺が必要です。治療は、低リスクの場合は無治療経過観察や輸血、エリスロポエチン製剤の注射を投与することがあります。高リスクの場合は、アザシチジンという抗がん剤の投与や造血幹細胞移植が考慮されます。
原発性骨髄線維症
原発性骨髄線維症は、骨髄内に線維組織が増殖し、正常な造血機能が阻害される病気です。JAK2遺伝子の変異が関連していることが多く、貧血や脾臓の腫れ、体重減少、発熱などの症状が現れます。血小板数は減ることもあれば増えることもあります。
診断には血液検査、JAK2遺伝子変異の検査、骨髄検査での骨髄線維化の確認が必要です。無症状の場合は無治療経過観察のこともあります。治療にはJAK2阻害剤、高リスク例では骨髄移植などの造血幹細胞移植が考慮されます。
急性白血病
急性白血病は、未熟な白血球が「がん化」し、異常に増殖する病気です。主に、急性骨髄性白血病と急性リンパ性白血病にわけられます。原因は明らかではありませんが、放射線や抗がん剤、化学物質への暴露などが関与します。まれに、遺伝的な要因があることも知られています。発熱や疲労感、貧血、出血傾向などの症状が現れ、診断には血液検査や骨髄検査が必要です。治療には抗がん剤治療が主に行われ、必要に応じて骨髄移植などの造血幹細胞移植も検討されます。
この病気が疑われた場合は、早急な治療が必要なため連携する医療機関に紹介いたします。
ヘパリン起因性血小板減少症
抗凝固薬であるヘパリンに対する免疫反応により血小板が減少します。ヘパリン投与後に血小板数が急激に低下しますが、出血はまれで血栓形成のリスクが高まります。診断には血小板数の測定と抗HIT抗体の検査が行われ、治療はヘパリンの中止と抗凝固療法の変更が必要です。
薬剤性血小板減少症
特定の薬剤が血小板の産生を抑制したり、免疫による破壊を促進することによって引き起こされる状態です。抗生物質や抗がん剤、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)、抗てんかん薬が原因となることがあります。症状は出血傾向が中心で、血液検査で血小板数の低下が確認されます。治療の基本は原因薬剤の中止です。
先天性血小板減少症
遺伝的な要因により血小板の産生が不十分である状態です。Wiskott-Aldrich症候群やBernard-Soulier症候群などが代表的です。症状には出血傾向や紫斑が見られ、家族歴が重要な手がかりとなります。診断には血液検査や遺伝子検査が行われ、治療は対症療法、輸血、骨髄移植などの造血幹細胞移植を検討します。
偽性血小板減少
機械での血小板数の測定時に、真の血小板数よりも低く測定されてしまう可能性があります。採血が取りにくい方などで採血に時間がかかると、採血管の中で血小板が凝集し、大きな塊となってしまいます。この塊となった血小板が機械で白血球と誤認されるため、実際よりも血小板数が低く測定されてしまいます。
また、採血は問題なく行えたにもかかわらず血小板が凝集する場合は、EDTA依存性偽性血小板減少症が疑われます。これは、体の中でおきる反応ではなく、採血管の中のみ起こる反応です。EDTAとは採血管の中にある、血液が固まらないようにする薬剤です。EDTA依存性偽性血小板減少症が疑われた場合は、採血直後に測定するか、別の抗凝固剤(ヘパリン、クエン酸ナトリウムなど)が入った採血管を用いる必要があります。
「血小板が少ない」に関するよくある質問
血小板が少ない場合、食事で気をつけることはありますか?
特別気をつける必要はありませんが、血小板の形成に関わるビタミンB12、葉酸を含む食品を積極的に摂取し、バランスの良い食事が推奨されます。例えば、赤身の肉、魚、豆類、緑黄色野菜などが良いでしょう。ただし、具体的な食事制限が必要な場合もあるため、医師や栄養士に相談することが大切です。
血小板が少ない場合、飲酒はどう影響しますか?
飲酒は血小板の機能に影響を与えることがあります。特に大量に飲酒すると、血小板の機能が低下し、出血傾向が強まる可能性があります。医師と相談し、適切な飲酒量を守ることが推奨されます。
血小板が少ない場合、運動はしても大丈夫ですか?
血小板が少ない場合、激しい運動や危険なスポーツは避けるべきです。しかし、医師が許可すれば軽い運動は問題ないことがあります。出血のリスクがあるため、運動を行う際は慎重に判断することが重要です。
血小板が少ないと妊娠に影響はありますか?
血小板が少ない場合、妊娠や出産に影響を与える可能性があります。特に、出血傾向が強い場合には、妊娠中のリスクが高まるため、妊娠を希望する場合は血液内科専門医の当院医師までご相談ください。
血小板が少ないことは遺伝しますか?
一部の血小板減少症は遺伝的要因が関与していますが、すべてのケースが遺伝によるものではありません。特に、先天性血小板減少症(例: Wiskott-Aldrich症候群など)は遺伝が関連していますが、後天的な原因も多く存在します。
血小板が少ない状態は治療によって完全に治りますか?
血小板減少症の治療は、原因に応じて異なりますが、原因が特定され、適切な治療が行われることで、血小板の数が正常に戻ることが期待できます。ただし、自己免疫性疾患や慢性疾患の場合、長期的な管理が必要となることがあります。
血小板が少ないときの合併症にはどんなものがありますか?
血小板が少ないと、出血傾向が増し、内出血や外傷後の出血が止まりにくくなることがあります。重症の場合には、脳内出血や消化管出血などの重大な合併症が発生する可能性があります。
血小板が少ない状態が続くと、どのような影響がありますか?
血小板が持続的に少ない場合、慢性的な出血や内出血が発生しやすくなるため、生活の質が低下する可能性があります。
血小板が少ないとき、避けるべき薬剤はありますか?
血小板が少ない場合、出血リスクを高める可能性のある抗凝固薬や鎮痛薬(特にアスピリンなどの非ステロイド性抗炎症薬)の内服は注意が必要であり、医師とよく相談するようにしましょう。
血小板数の低下を引き起こすウイルス感染にはどのようなものがありますか?
血小板数の低下を引き起こすウイルス感染には、HIV、肝炎ウイルス、風疹ウイルス、EBウイルスなどがあります。これらのウイルスは、骨髄に影響を与えたり、血小板の寿命を短くしたりします。